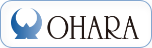Q&A
Q&A検索
メグルダーゼ®についてのよくあるご質問
保管管理
- 凍結乾燥製剤ですが1℃(0℃以下含む)以下で保存できないのでしょうか?1℃(0℃以下含む)以下で保存してしまったものは使用できませんか?
本剤は2~8℃で保存した場合の安定性データがあり、品質を保証できる温度範囲は2~8℃です。
1℃(0℃以下含む)以下で保存した場合の安定性データはございませんので、この温度で保存された製剤の品質は担保できません。
- 「溶解後やむをえず保存する場合は、バイアル内にて2~8 ℃で保存し、調製から4時間以内に投与を開始すること。」と記載されていますが(添付文書「14.1.3」)根拠のデータはありますか?
- 各種使用時安定性試験の結果から4時間の安定性を確認しています。
組成・性状
- 充填量はどの程度ですか?
- バイアル当たり1,000Uとなるように充填されており、その充填量は製造過程や品質試験によって管理されています。
- トロメタモールの添加意義は?
- pH緩衝剤です。
- pHが弱アルカリ性ですがカテーテル等への影響はないですか?
- 本剤を生理食塩液に溶かした液とカテーテル等との適合性データはございません。
本剤は再調製(溶解させて再び薬液に調製)した際に、酵素活性の至適pH付近となる弱アルカリ性になるように処方化されています。また、本剤のpHは静脈内pHに近く、望ましい範囲にあります(生理食塩液1mLを加えて溶解した液のpHは7.1-7.9)。
- 添付文書「3.2 製剤の性状」において注2と注3で生理食塩液に日局の有無が異なるのはなぜですか?
- pHの測定は海外での試験結果に基づいており、日局生理食塩液を用いて測定していないため、記載が異なります。
効能又は効果、効能又は効果に関連する注意
- 小児にも使用可能ですか?
- 小児にも使用可能です。
PMDAとの審査においても、①成人及び小児患者を対象とした試験結果より、成人と小児との間で本剤の有効性及び安全性に明らかな差異は認められないと考えられること、②本剤はタンパク製剤であり、成人と小児との間で本剤のPKに差異が生じる可能性は低いと考えたこと等の理由が適切であると判断されたことから、年齢区分が設けられていません。
- LVの救援療法以外は使用できませんか?
- 使用できません。
国内外で実施した臨床試験は、全てMTX・LV救援療法を受けた患者が対象であり、また、それ以外のMTXを用いた療法におけるデータについては、PMDAにより審査されていません。
- 添付文書「5.2 本剤投与の目安となる血中メトトレキサート濃度」において、急性腎障害の徴候なし・ありと記載されていますが、急性腎障害の基準は何ですか?
- 添付文書「17.1.1 国内第Ⅱ相試験(CPG2-PⅡ試験)」の注1(ii)に記載のCPG2-PⅡ試験における急性腎障害の徴候の基準を目安としてご参照ください。
なお、本剤の審査報告書においてPMDAの見解として、血中MTX濃度に加えて、患者の状態等も考慮した上で本剤の投与の要否を判断することが適切である旨が記載されています。
- 投与目安となる血中MTX濃度は腎障害の徴候によって異なりますが、粘膜障害などは考慮しなくても良いのでしょうか?
- 患者の状態として場合によっては考慮しても良いと考えます。
本剤の審査報告書においてPMDAの見解として、血中MTX濃度に加えて、患者の状態等も考慮した上で本剤の投与の要否を判断することが適切である旨が記載されています。
用法及び用量
- 本剤の投与量が50U/kgに設定された根拠はありますか?また、本剤投与量の上限はありますか?
審査報告書に下記記載がございます。
「米国において、006試験等の成績に基づき本薬が承認されていることを踏まえ、本邦では、米国での承認用法・用量を参考に、健康成人を対象とした国内第Ⅰ相試験(CPG2-PⅠ試験)における本薬の用法・用量を20又は50U/kgと設定した。①CPG2-PⅠ試験の結果から日本人と外国人との間で本薬50U/kg投与時のPKに明確な差異は認められなかったこと、②成人及び小児患者を対象とした006試験等の結果より、成人と小児との間で本薬の有効性及び安全性に明らかな差異は認められないと考えたこと、③本薬はタンパク製剤であり、成人と小児との間で本薬のPKに差異が生じる可能性は低いと考えたこと等から、CPG2-PⅡ試験の本薬の用法・用量は、006試験と同様に、成人及び小児のいずれに対しても本薬50U/kgを5分間かけて静脈内投与すると設定された。当該設定により実施されたCPG2-PⅡ試験において、本薬の臨床的有用性が認められたことから、当該試験の設定に基づき、本薬の申請用法・用量を設定した。」また、投与量の上限について、海外コンパッショネートユース試験では投与量上限を2,000Uとしていましたが、国内第Ⅱ相試験においては本剤投与量の上限は設定されていません。
- 「50U/kgを5分間かけて静脈内投与」と記載されていますが(添付文書「6」)、投与時間の長短によって不具合が生じるのでしょうか?
- 評価された(申請に使用した)全ての臨床試験において、50U/kgを5分間かけて投与していますので、投与時間の長短による不具合に関するデータはございません。
- 5分以上かけて投与することはできませんか?
- 5分間かけて投与したデータにて、本剤の用法及び用量が承認されていますので、5分以上かけて投与することはできません。
- 投与時間が5分間であれば、点滴静注あるいは、中心静脈投与等での投与は可能ですか?
- 投与時間が5分間で、かつ、静脈内投与であれば、どのように投与されても問題ございません。
- 体重が少ない場合OneShot投与はできますか? (体重20kgで1,000U使用、薬液としては1mL)
- 本剤は体重が少ない場合でも5分間かけて投与しています。そのため、OneShot投与の使用経験はございません。
- LVと併用しないのはなぜですか?
- In vitro試験及び海外で行われた健常人対象の第I相試験より、本剤はLVの活性異性体である(6S)-LVを分解することが確認されています。そのため、本剤との相互作用を最小限に抑える目的でLVと併用していません。ヒトにおけるLVの活性異性体の半減期は約35分であるため、本剤投与の2時間以上前にLVを投与すると本剤によるLVの代謝が最小限に抑えられると考えられるため、添付文書には、「ロイコボリンは本剤投与の前後それぞれ2時間以上の間隔を空けて投与すること」と記載されています。
- 1回目の投与でMTX濃度が下がらない場合、引き続き本剤の投与は可能でしょうか?
- 添付文書上、追加投与は認められています。本剤投与48時間後の血中MTX濃度を確認の上投与してください。
- 再投与(別サイクル)は可能でしょうか?
- 審査報告書には再投与が許容されると考える、と記載されています。
保険に関しては各都道府県の審査機関へのお問い合わせをお願い致します。
MTX・LV救援療法、支持療法
- 本剤投与完了後のLV救援療法、支持療法の具体的な投与手順で留意すべきことはありますか?
- LVは本剤投与の前後それぞれ2時間以上の間隔を空けて投与してください。また、LVの用法・用量については添付文書「8.1.2」をご参照ください。
(・本剤投与後48時間以内の投与では、本剤投与前と同一とすること。・本剤投与後48時間以降の投与では、各測定時点における血中MTX濃度に基づき決定すること。)(LVは前後2時間空けて投与してください)
- 本剤投与前後2時間以内にLVを投与した場合、LVへの影響に関するデータはありますか?
- 治験では、本剤投与前後2時間以上空けてLVを投与しています。
そのため、本剤投与前後2時間以内にLVを投与した使用経験はございません。
- 「ロイコボリン救援療法の継続の要否は複数回の血中メトトレキサート濃度測定に基づき判断する」と記載されていますが(添付文書「8.1.3」)、回数とタイミングの具体的な目安はありますか?
- 特にはございません。
ご施設におけるMTX・LV救援療法を実施される際の手順に従い、血中MTX濃度測定を行ってください。
- 結晶尿の予防として尿のアルカリ化を行うのでしょうか?
- 本剤投与によって生じるDAMPAによる結晶尿が発現する可能性があることから、支持療法として、尿のアルカリ化が添付文書に記載されています。
- 尿のアルカリ化、利尿剤の投与は絶対に必要ですか?
- 必要です。
本剤は、MTX・LV救援療法時に使用することから、MTXの添付文書に記載されている内容に沿った処置が必要です。
(記載内容:「過量投与したときは、すみやかに本剤の拮抗剤であるホリナートカルシウム(ロイコボリンカルシウム)を投与するとともに、本剤の排泄を促進するために水分補給と尿のアルカリ化を行うこと。」)
- 支持療法として投与された併用薬剤とは、どのような薬剤が該当するのでしょうか?
CPG2-PⅡ試験の治験総括報告書、投与量及び投与スケジュールでは支持療法(LV以外)は以下の通りに規定されています。
1)利尿剤はアセタゾラミド(ダイアモックス®)以外は原則として使用しないで下さい。(特にループ利尿薬、マンニトールは血中MTX濃度が0.3μmol/L以下となるまでは許容されない)
輸液組成は指定しませんが、腎機能が正常の時にはカリウムが低下することに注意して下さい。
腎機能低下のためアセタゾラミドを用いても尿量を確保できない場合は、アセタゾラミドを継続投与しながら、極端に体重増加しないように時間尿量の1.2-1.3倍を目安に輸液を継続します。2)炭酸水素ナトリウムを輸液に加え、尿pHを7未満としないようにする。
尿pHは12時間に1回以上確認し(4-8時間に1回を目安とするとが、安定している場合は朝夕の2回とする)、高Na血症などアルカリ化が困難な場合は休止して下さい。
- アセタゾラミドを使用しても排尿障害、高度な浮腫が進行する場合はどのように対処すれば良いですか?
- 腎不全による排尿障害、高度な浮腫の進行など、大量輸液が困難な場合は、輸液量の減弱や禁止薬であるラシックスの使用を検討します。
更なる腎機能低下が続き、臨床的に腎不全に進行する(CREの上昇が続く、乏尿が続く、電解質異常の補正困難、体重増加持続、尿毒症症状があるなど)場合は透析導入を検討して下さい。既に透析導入されている場合には、プロトコール治療としての指定はありません。
血中MTX濃度測定
- 血中MTX濃度を正確に測定するために「EDTA-2Na、クエン酸ナトリウム等が含まれる採血管を用いて採血すること。」とありますが、これらを用いる根拠(加水分解反応を止める)データはありますか?
- 本剤は亜鉛要求性の酵素である旨が報告されていること(Ther Clin Risk Manag 2012;8: 403-13)、及び酸性条件下では本剤によるMTXの分解反応が停止することを踏まえ、in vitro において、EDTA-2Na、クエン酸ナトリウム等を添加した採血管を用いて採取したヒト血漿とMTXを、本剤存在下において氷冷で24時間保存した結果、MTX濃度の低下は認められませんでした。そのため、EDTA-2Na(エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム)、クエン酸ナトリウム等が含まれる採血管を用いるよう設定されています。
- 各社の検査キットはすべてイムノアッセイですか?
- はい。
- MTXの測定にはFC採血管が必要でしょうか?
- 必要です。
FC採血管を使用することで、本剤の加水分解反応を止めることができます。
本剤が血中に残存している場合、採血後にもMTXの加水分解反応が引続き起こっている可能性があり、血中MTX濃度を正しく評価できない可能性が考えられるため、本剤投与後の血中MTX濃度を評価する際には、FC採血管をご利用ください。
- イムノアッセイを用いた血中MTX濃度測定が過度に測定される場合があるとのことですが、その測定値を中央測定値の手法であるLC-MS/MS法、またはHPLC法での測定値に換算することは可能ですか?
- イムノアッセイ法を用いた検査値は、HPLCの実測値より高い値が測定されることを念頭に置いたうえで、MTX毒性(副作用)の程度等を加味して、治療継続の判断をお願いいたします。
特定の背景を有する患者
- 添付文書「9.7 小児等」項目の欠番がありますがなぜですか?
- 本剤は、添付文書の記載要領における「小児等に特殊な有害性を有すると考えられる場合や薬物動態から特に注意が必要と考えられる場合」には該当しないため、「9.7小児等」の項目は欠番となっています。
なお、MTX・LV救援療法の施行によりMTX排泄遅延が認められた患者を対象とした主な国内臨床試験であるCPG2-PⅡ試験においては、15例中7例が15歳未満の小児患者でした。
- 妊婦、授乳婦への投与については、MTXでも注意喚起されていると思いますが、どのような注意喚起を行うのでしょうか?
- 妊婦、授乳婦にMTXを使用する際、十分なインフォームドコンセントを行っているものと考えます。その上で、本剤を使用する必要がある場合は、添付文書「9.5 妊婦」若しくは「9.6 授乳婦」に記載されている内容を基に、追加の注意喚起をお願いいたします。
薬剤調製・投与
- 追加投与が可能となる48時間後の1μmol/Lの設定について、エビデンスがあれば教えてください。
本臨床試験において追加投与が48時間値で1μM/mLをカットオフにしている理由は判明しませんでした。
但し、TDMの対象薬剤であるメトトレキサートの中毒域は24時間10.00μmol/L以上、48時間1μmol/L以上、72時間0.10μmol/L以上であり、追加投与においては一旦低下したメトトレキサートのリバウンドを考慮して48時間で1μmol/Lをカットオフにしたと考えられます。(メグルダーゼ投与後48時間程度はメトトレキサートとDAMPAがコンタミネーションを起こす事からイムノアッセイ法での検出は48時間以降となっています)
- 投与スケジュールにおける本剤投与時に支持療法の投与はしていませんか?
- 本剤投与時においてもMTXの副作用に対する支持療法は実施されており、本剤添付文書にもその旨が記載されています。
- 「本剤1バイアル(1,000U)を日局生理食塩液1mLで溶解後、適量の日局生理食塩液にて希釈して使用する。」と記載がありますが、臨床試験では3バイアルを使用する場合、全量はどれくらいでしたか?
- 治験時には下記にて対応していたようです。「投与する際の希釈液を含む全量の指定はないが、予定投与量を5分で投与する(例:全量が10mLとなるように生理食塩水で希釈し、シリンジポンプを用いて120mL/hで投与する)」
- 生理食塩液以外で希釈できないのでしょうか?
- 本剤を生理食塩液以外で希釈して検討したデータはございません(臨床試験、溶解液や使用時の容器との適合性等)。
- (添付文書「14.1.1」の記載に関して)投与時間5分として、希釈量の範囲の規定はありますか?
- 特に規定はございません。
- 未使用残液の廃棄方法に注意はありますか?
- 高薬理活性物質等は含まれていません。施設の廃棄方法に従って、医療廃棄物として廃棄してください。
- フラッシングは生理食塩液で良いでしょうか?
- 日局生理食塩液で行ってください。
- 注射針で直接静注はできないのでしょうか?
- 可能ですが、5分かけて投与できるようにしてください。
- 投与に際し、フィルターは必要ですか?
- 承認までの臨床試験においてフィルター処理した実績はございません。
データがないため判断いたしかねます。
- フィルター透過性やフィルターへの吸着性に関するデータはありますか?
- 承認までの臨床試験においてフィルター透過性やフィルターへの吸着性に関するデータはございません。
薬物動態
- 国内第Ⅱ相試験(CPG2-PⅡ試験)のMTXの薬物動態のグラフにおいて、48時間の血中MTX濃度(中央測定値)が24時間の測定値に比べて上昇しているのはなぜですか?
- グルカルピダーゼは血中のMTXを速やかに分解します。この作用は約48時間持続すると考えられています。しかしながら、組織に分布しているMTXは分解することができないことから48時間以降に組織のMTXが血中に戻ってくるリバウンド現象が観察されることが知られています。
- BBBの通過性はどの程度ですか?
- 本剤のBBBの通過性は評価しておらず、該当資料はございません。
しかし、本剤は分子量約83,000と高分子量の組み換えタンパク質であり、一般的にタンパク質は細胞膜を透過しないと考えられます。
- 細胞内への移行性に関するデータはありますか?
- 本剤の細胞内への移行性は評価しておらず、該当資料はございません。
しかし、本剤は分子量約83,000と高分子量の組み換えタンパク質であり、一般的にタンパク質は細胞膜を透過しないと考えられます。
本剤は高分子量のタンパク質であり、細胞内へ移行せず血中で分解されると考えられており、当該試験を実施する必要性はないと考えられました。
- DAMPAを分離する測定法は?
- HPLC(UV法、蛍光法、LC-MS/MS法など)を用いれば、DAMPAとMTXを区別して測定することが可能です。カラムを使用し、血漿からDAMPAを除く方法が報告されています(回収率が5割から7割となっています)。
- DAMPAの半減期はどのくらいですか?
- 測定条件によって多少変動しますが、国内で行われた患者を対象にした第Ⅱ相試験(CPG2-PⅡ試験)では約19時間(平均値)でした。
臨床成績
- MTX投与開始から本剤初回投与までの経過時間に関する治験データはありますか?
- 海外試験であるPR001-CLN-006試験についてはデータはございます(過半数においてMTX投与開始から72時間以内に本剤初回投与を受けました)が、国内試験におけるデータはございません。
- 投与後の腎機能改善についての有効性データはありますか?
- 本剤の有効性確認試験では、本剤投与後の腎機能改善評価をしておりません。
- PR001-CLN-006試験では、施設内測定MTX解析集団が134例もあるのに、主要評価項目は中央測定MTX HPLC解析集団27例で行われたのはなぜですか?
- 本剤の有効性を評価するためには、血中MTX濃度を正確に測定する必要があります。そのため、主要評価項目の解析は中央測定MTX HPLC解析集団で行いました。
(本剤を投与することで、DAMPAが産生されます。DAMPAは、施設測定において交差反応を示すことから、正確な血中MTX濃度を評価することができません。)
- PR001-CLN-006試験におけるリバウンド後のMTX濃度は、その後どのように回復したのですか?
- PR001-CLN-006試験において、中央測定MTX HPLC解析集団27例の内4例にリバウンドが起こりました。その内2例はリバウンド後48時間程度、1例は72時間程度で、血中MTX濃度が1 μmol/L以下に低下しました。残りの1例は、本剤投与48時間後に追加投与を受け、追加投与48時間後に血中MTX濃度が1 μmol/L以下に低下しました。
- PR001-CLN-006試験の副次評価項目について、記述統計量で算出とありますが、記述統計量とは何ですか?
- データの要約として表示する指標の事を指します。
PR001-CLN-006試験では「連続変数については被験者数(例数)、平均、標準偏差、中央値、最小値、最大値、カテゴリカル変数については各カテゴリーにおける被験者数(例数)と割合」が該当します。
- 国内第Ⅱ相試験(OP-07-001試験)は、対象患者4例で行われていますが、この試験の意味、位置づけは何ですか?
- CPG2-PⅡ試験の有効性評価において、血液検体中の本剤の酵素活性を失活させなかったことから、採血後に本剤による加水分解が継続している可能性があり、有効性評価結果を過大評価している可能性があることをPMDAから指摘されたため、CPG2-PⅡ試験結果の類似性(血漿中MTX濃度の低下率の類似性)を確認する目的で試験を行いました。
- 抗体産生の比率は?
- PG2-PI試験においては、本剤投与1、3及び6ヵ月後に、コホート1でそれぞれ8例中4例(50.0%)、4例中3例(75.0%)及び3例中3例(100.0%)が抗グルカルピダーゼ抗体が陽性であり、コホート2でそれぞれ8例中7例(87.5%)、7例中7例(100.0%)及び7例中6例(85.7%)で抗グルカルピダーゼ抗体が陽性でした。
CPG2-PⅡ試験においては、本剤投与前、本剤投与1、3及び6ヵ月後に、それぞれ15例中2例(13.3%)、15例中5例(33.3%)、15例中2例(13.3%)及び13例中2例(15.4%)で抗グルカルピダーゼ抗体が陽性でした。
PR001-CLN-005試験においては、腎機能障害を有する患者では4例中2例(50.0%)、腎機能が正常な患者では8例中5例(62.5%)で、全体では12例中7例(58.3%)で抗グルカルピダーゼ抗体が陽性でした。いずれの患者もDay0及びDay7の時点では、抗グルカルピダーゼ抗体は陰性でした。抗グルカルピダーゼ抗体の発現には、腎機能が正常な患者と重度の腎機能障害を有する患者との間で、臨床的に重要な違いはないと考えられました。
副作用
- 製品情報概要p.13に記載の、MTX関連有害事象の腎機能障害の進行はどの程度ですか?症状の消失や軽快等の判断はされていますか?
- 腎機能障害の進行については、Gradeは判定されていないため、進行がどの程度か等はわかりかねます。症状の改善としては、安全性解析対象集団において,腎機能障害の指標である血清クレアチニン(平均値±標準偏差)は,ベースラインでは1.229±0.886mg/dLであり,本剤投与後4日目に1.869±1.784mg/dLまで上昇した後,投与後8日目まで維持された。その後,投与後11日目でベースライン値に戻り,それ以降は投与後21日目までにベースライン値より低下したことがわかっています。
その他
- 本剤投与の有用性を示すデータはありますか?また、本剤の投与意義について教えてください。
メトトレキサート・ロイコボリン救援療法の施行によりメトトレキサート排泄遅延が認められた成人及び小児患者15例(有効性の解析対象13例)を対象に、本剤の有効性、安全性等を検討するためCPG2-PⅡ試験を実施した。その結果、主要評価項目であるCIR(Clinically Important Reduction)(本剤投与開始20分後から4日後までのすべての採血時点で中央測定による血漿中メトトレキサート濃度が1μmol/L未満)達成割合[95%信頼区間](%)は、76.9[46.2, 95.0](10/13例)であった。副作用は、本剤が投与された15例中 2 例(13.3%)に認められ、過敏症及び血中ビリルビン増加が各 1 例(6.7%)であった。これらの結果等から、MTX・LV救援療法の施行によりMTX排泄遅延が認められた患者に対する本薬の臨床的有用性が認められた。
投与意義としましては、審査報告書内に下記記載がございます。「HD-MTX療法はMTXの大量投与により、腎機能障害が発現し、MTXの排泄が遅延することで重篤なMTX中毒が発現する可能性があることから、MTXの毒性軽減を目的としたLVの投与や、MTXの排泄促進を目的とした大量輸液、尿のアルカリ化、利尿剤の投与等の支持療法が実施されている。しかしながら、これらの治療が実施された場合であっても、血中MTX濃度の低下が不十分な場合があり、重篤なMTXによる毒性が発現するリスクがある。なお、LVによる救援療法や支持療法を実施しても血中MTX濃度の低下が不十分な場合には、血中MTXの除去を目的とした血液浄化療法の実施が検討されているものの、血液浄化療法は MTXの除去に長時間を要する等の問題がある。以上より、MTX排泄遅延が認められた患者に対する新たな治療選択肢が求められている。 以上のような状況において、CPG2-PⅡ試験の結果等から、MTX・LV救援療法の施行によりMTX排泄遅延が認められた患者に対する本薬の臨床的有用性が認められたことから、本薬は当該患者に対する治療選択肢の一つとして位置付けられると考える。」
- DAMPAの腎障害への影響について教えてください。
- 安全性薬理試験において、尿検査及び肉眼的観察の結果から腎臓に明らかな影響は認められなかったことが記載されています。
- DAMPAの排泄経路について教えてください。
- 安全性薬理試験より、本剤が加水分解することで生じるDAMPAは未変化体として約46%が腎排泄されることがわかっています。また、DAMPAの99%超は10時間後までに血漿から消失することから、DAMPAの約50%は腎排泄される経路の他に代謝される可能性が報告されております。
- DAMPAの毒性について教えてください。
- DAMPAの細胞毒性およびMTX細胞毒性に対する効果を、ヒト白血病細胞株Molt-4で評価した結果、DAMPAは細胞毒性を示さず、MTXの細胞毒性に影響を及ぼしませんでした。
- 添付文書「16.7 薬物相互作用」に記載があるにも関わらず、「10. 相互作用」項目が欠番しているのはなぜですか?
- PMDAは、本剤の基質となる薬剤と本剤との薬物動態学的相互作用に関する情報は、本剤の適正使用のために重要と考えたため、16.7章に記載するよう指示がありましたが、10章への記載については、指示されませんでした。
- 他の抗がん剤等への影響はないのでしょうか?
- 現時点において、特定されたリスクはございません。
ただし、ペメトレキセドは本剤の基質となることが示されており、プララトレキサートは本剤の基質となる旨の報告はないものの本剤の作用部位であるカルボキシ末端のグルタミン酸残基を有することから本剤の基質となる可能性があります。
しかしながら、ペメトレキセド及びプララトレキサートが臨床において本剤と併用される可能性は低いことから、これらの薬剤との併用投与が本剤の臨床使用時に問題となる可能性は低いと考えられたため、相互作用欄に記載していません。
- 中和抗体産生の可能性はありますか?
- 中和抗体が産生される可能性がございますが、治験において測定していません。
- コマーシャルで抗グルカルピダーゼ抗体を測定できる検査センター(臨床検査会社等)を教えてください。
- 検査センターはございません。
- 抗グルカルピダーゼ抗体陽性だった場合、投与量の増量や投与中止などの具体的な規定はありますか?
- 規定はございません。
- 血管外漏出時における対応の情報はありますか?
- 情報はございません(高薬理活性物質は含まれていません)。
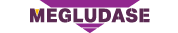 医療関係者向けサイト
医療関係者向けサイト