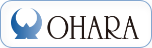使用方法
3. 参考:国内第Ⅱ相試験(CPG2-PⅡ試験)の治療法
1. 支持療法(尿のアルカリ化、十分な水分補給等)について
●本剤は、支持療法(尿のアルカリ化、十分な水分補給等)が実施されている患者に投与されました。
●125mL/m2/時間以上の輸液を行い、適宜利尿剤を用いて、100mL/m2/時間以上の尿量が得られるようにすることとされました。
なお、利尿剤はアセタゾラミド以外は原則として用いないこととされ、特にループ利尿薬やマンニトールは血中MTX濃度が0.3μmol/L以下となるまでは許容されないこととされました。また、輸液組成は指定しないが、腎機能が正常の時にはカリウムが低下することに注意することとされました。
●腎機能低下のため、アセタゾラミドを用いても尿量を確保できない場合は、アセタゾラミドを継続投与しながら、極端に体重増加しないように時間尿量の1.2-1.3倍を目安に輸液を継続することとされました。ただし、腎不全による排尿障害、高度な浮腫の進行など、大量輸液が困難な場合は、輸液量の減弱や禁止薬であるフロセミドの使用も検討することとされました。
●更なる腎機能低下が続き、臨床的に腎不全に進行する場合(Creの上昇が続く、乏尿が続く、電解質異常の補正困難、体重増加持続、尿毒症症状があるなど)は、透析を導入することとされました。
●炭酸水素ナトリウムを輸液に加え、尿pHを7未満としないようにされました。
なお、尿pHは12時間に1回以上確認(4-8時間に1回が目安だが、安定している場合は朝夕の2回)し、高Na血症などアルカリ化が困難な場合は休止することとされました。
●最後(1回のみの場合は1回目、2回投与した場合は2回目)の本剤投与後48時間以降のMTX濃度が0.3μmol/L未満となるまで継続されました。
●本剤投与中は支持療法による輸液は一時中止され、本剤の投与終了次第再開されました。
2. 本剤投与について
●本剤の投与に際して、体重の小数点第1位を四捨五入して50を乗じた値が投与量とされました。
●本剤は、直前のロイコボリン(LV)投与終了後2時間以上経過したのちに、採血ルート以外から5分間かけて投与されました。
3. 本剤投与後(48時間まで)の対応について
●本剤投与2時間後、ロイコボリン救援療法(LVR)が行われました。
●LV投与については、本剤投与前の血中MTX濃度に基づいた投与量・投与法が計画され、本剤投与後48時間まで変更せず継続することとされました。ただし、血中MTX濃度によるのではなく、臨床症状等による必要性がある場合は、LVの投与量増量もしくは投与間隔短縮等の変更が可能とされました。
4. 本剤投与後(48時間)の血中MTX濃度に基づく対応について
●本剤投与48時間後(±2時間)に血中MTX濃度が測定され、濃度に応じて、以下の対応を行いました。
【血中MTX濃度が1μmol/L未満の場合】 LVR継続
●本剤投与48時間後の測定による血中MTX濃度に合わせてLVの投与量・投与法が再調整されました。
●1日に1回(ただし1回目の本剤投与6日目以降は3日に1回以上でよい)血中MTX濃度を再検し、LVの投与量・投与法を再調整しながら、血中MTX濃度が0.1 μmol/L未満となるまで継続されました。
●治療開始後0.3μmol/L以下になったものの、4日以上0.1μmol/L未満にならない場合には、次に予定している抗腫瘍治療(クール)が開始可能となった場合(有害事象が消失するなど)にLVRを終了とすることも可能とされました。
【血中MTX濃度が1μmol/L以上の場合】 メグルダーゼ®再投与
●2回目の本剤投与が、1回目の本剤投与後50時間以上52時間以内を目安に、1回目と同じ投与量・投与法で実施されました。
●血中MTX濃度測定用採血は、1回目の本剤投与48時間後を起点に24時間後及び48時間後に実施されました。
●2回目の本剤投与2時間後に、LVRが再開されました。
●LVRの方法は、1回目の本剤投与48時間後の血中MTX濃度に基づき決定されました。
●1回目の本剤投与後96時間まではLVRの方法は変更しないこととされました。
●1回目の本剤投与96時間後の採血による血中MTX濃度に合わせて、LVRが再調整されました。
●1日に1回(ただし1回目の本剤投与6日目以降は3日に1回以上でよい)血中MTX濃度を再検し、LVの投与量・投与法を再調整しながら、血中MTX濃度が0.1μmol/L未満となるまでLVRが継続されました。
●以下の場合には、1回目の本剤投与後46時間以降での血中MTX濃度が1μmol/L以上であっても、2回目の本剤投与は行わないこととされました。
・1回目の本剤投与後にアナフィラキシーショックが生じた場合。
・1回目の本剤投与から54時間を経過して2回目の投与ができない場合。
・患者又は代諾者が本剤の投与中止を希望した場合。
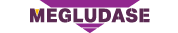 医療関係者向けサイト
医療関係者向けサイト